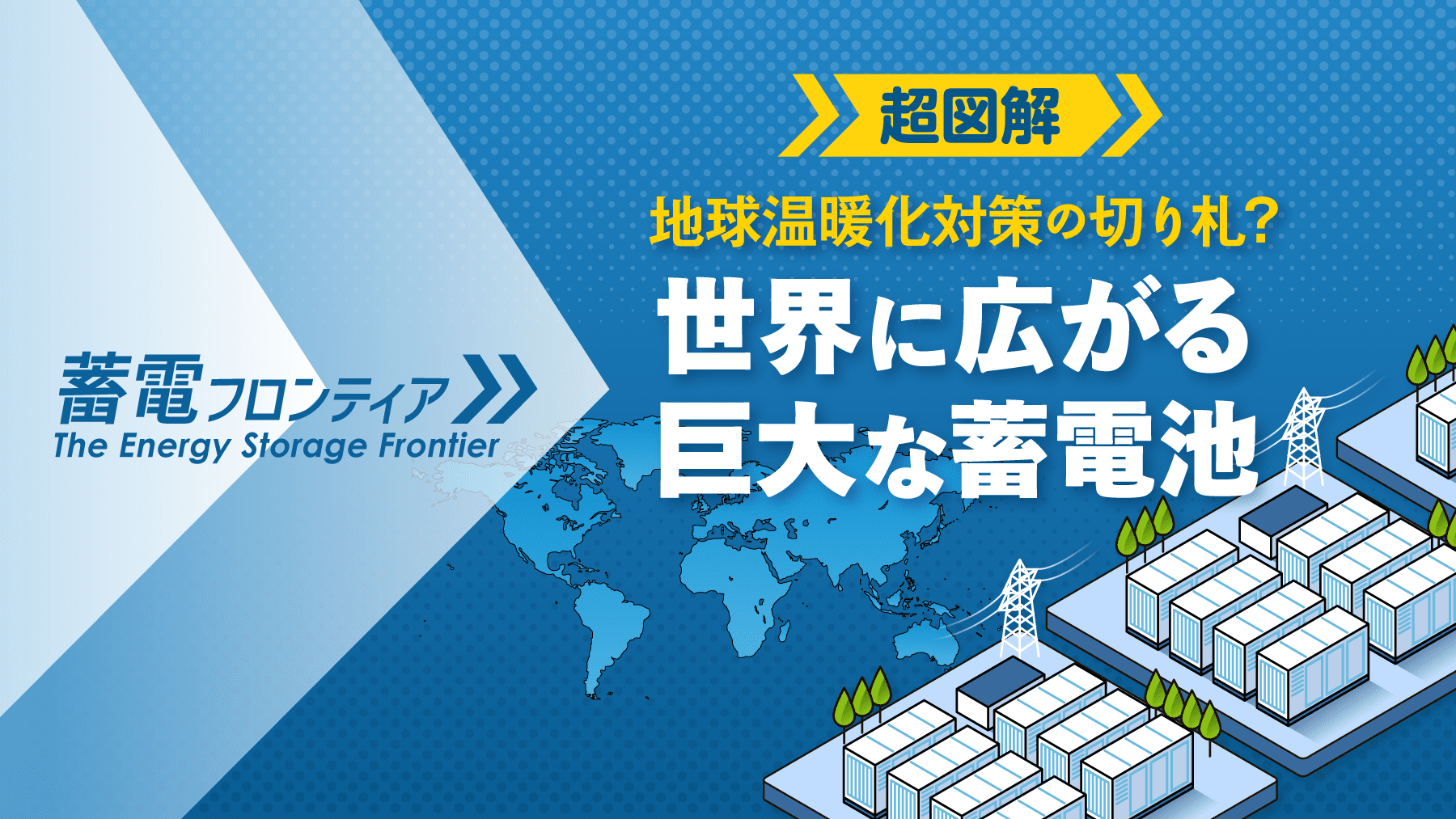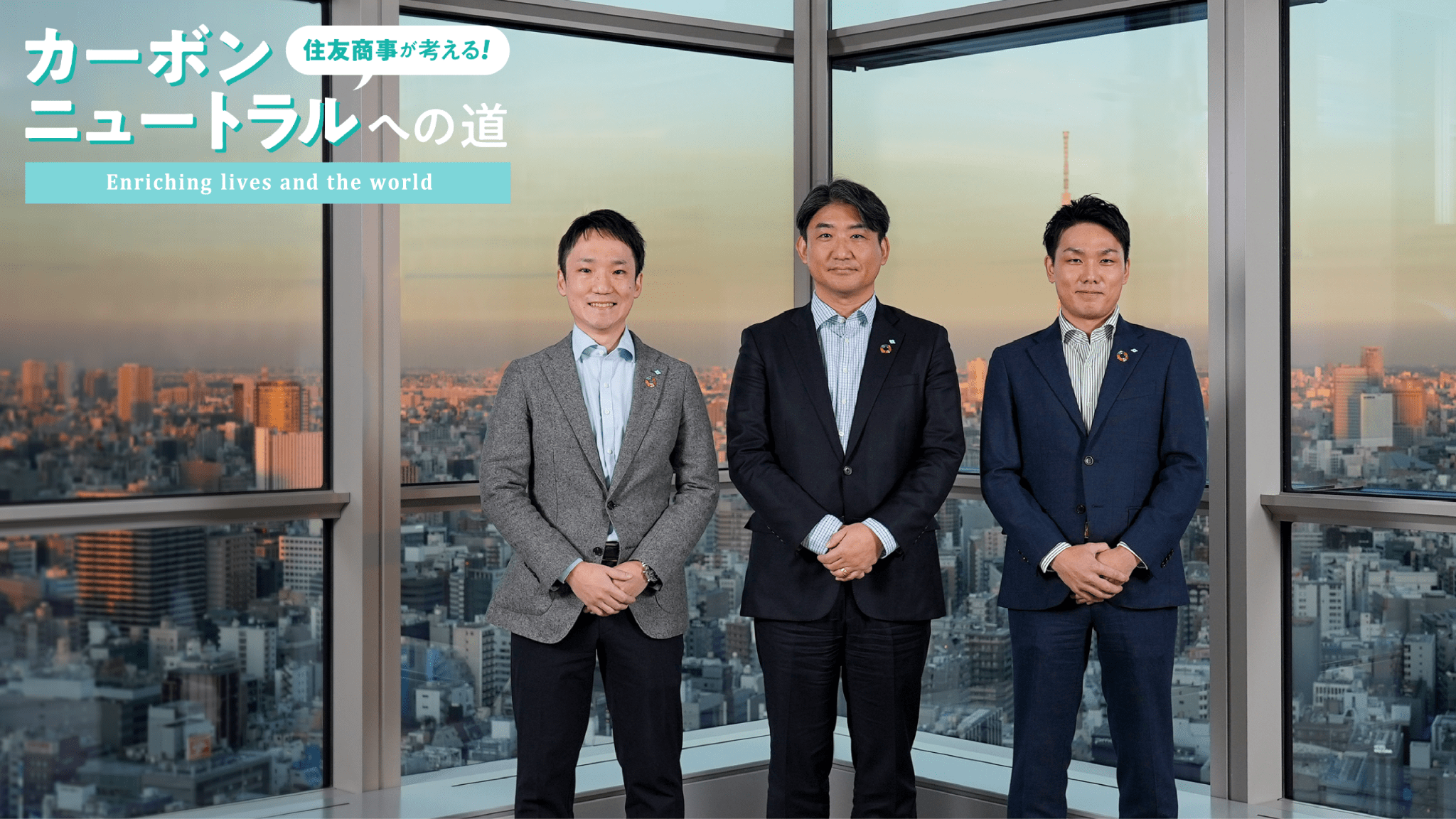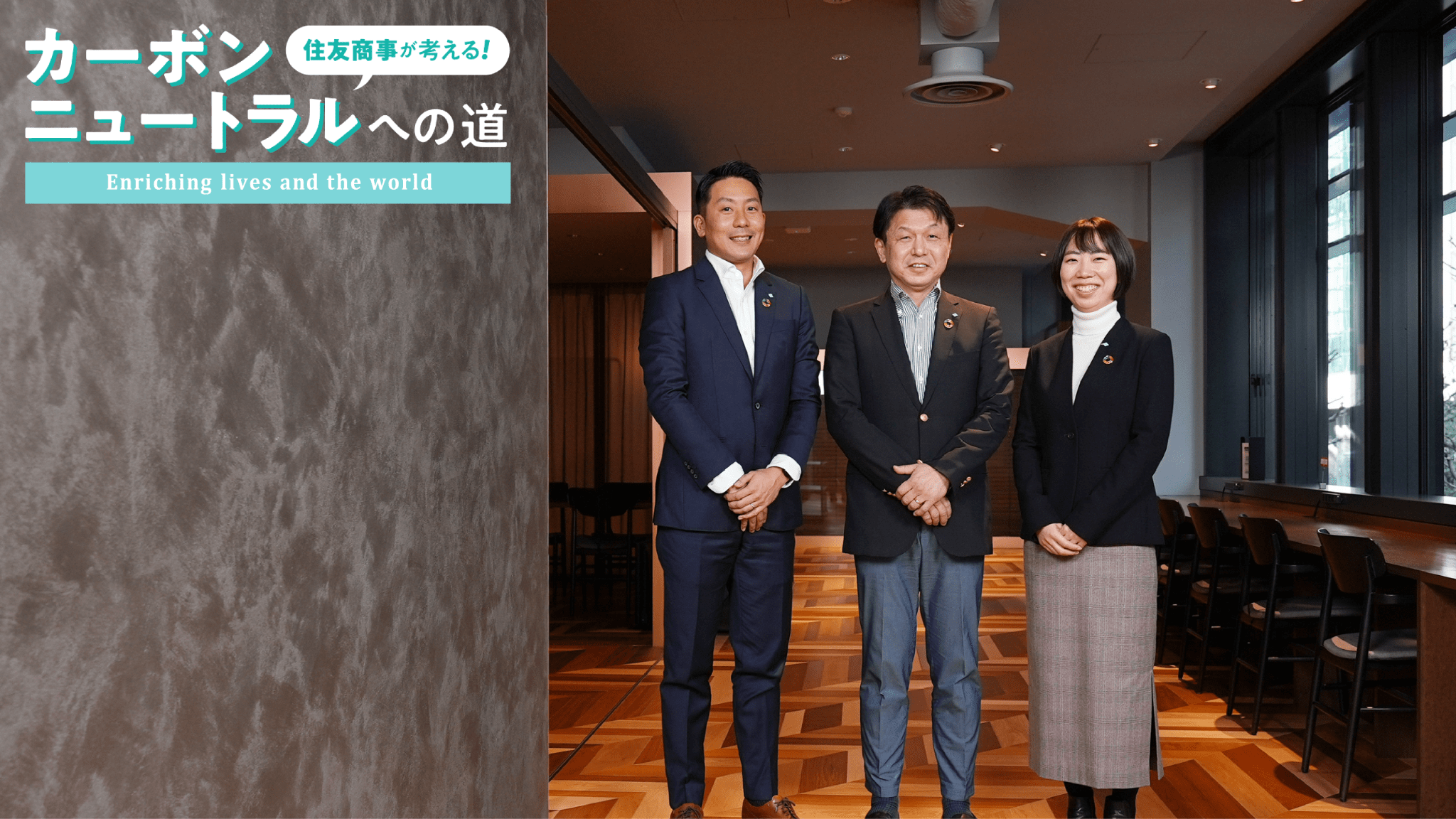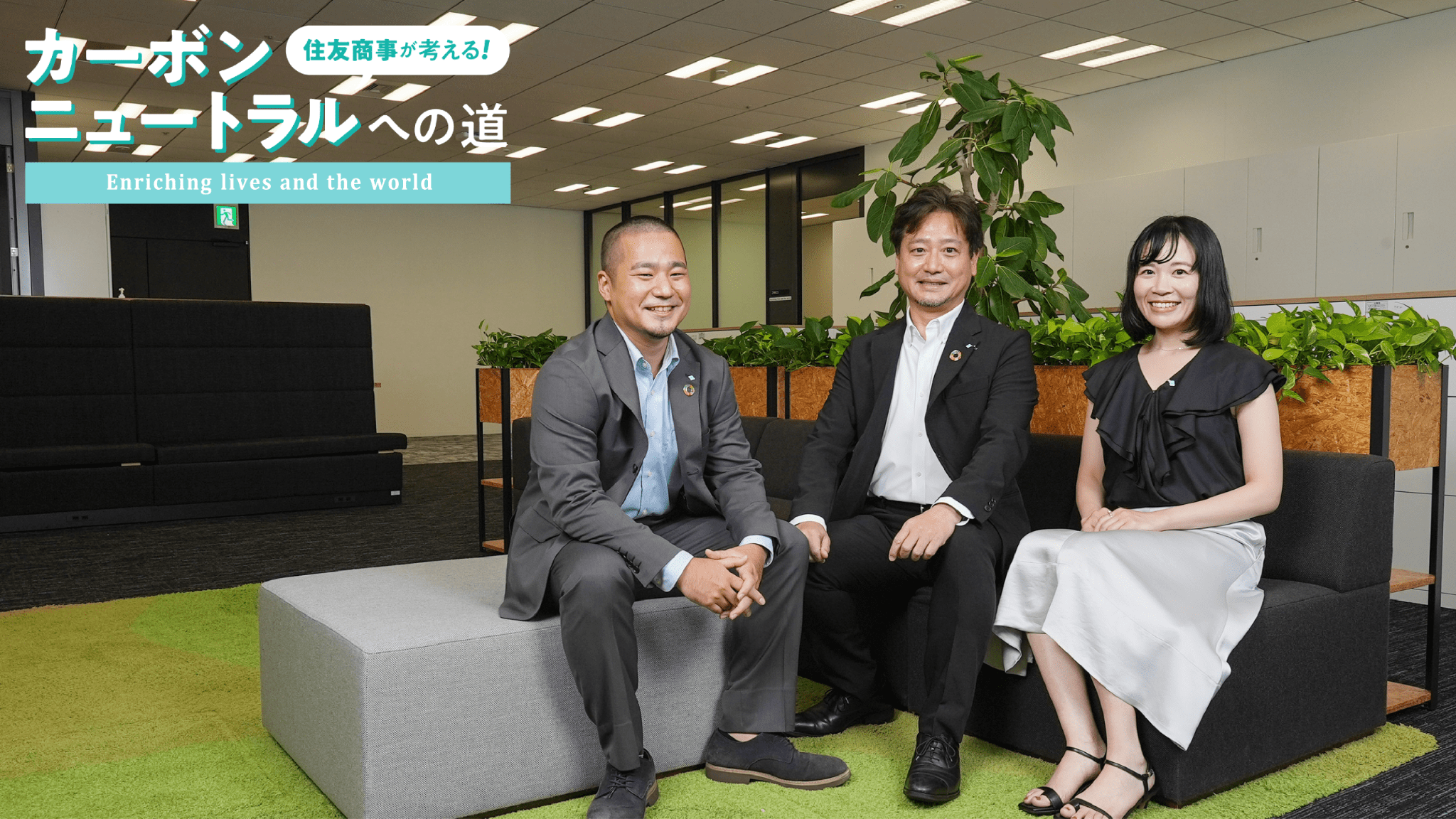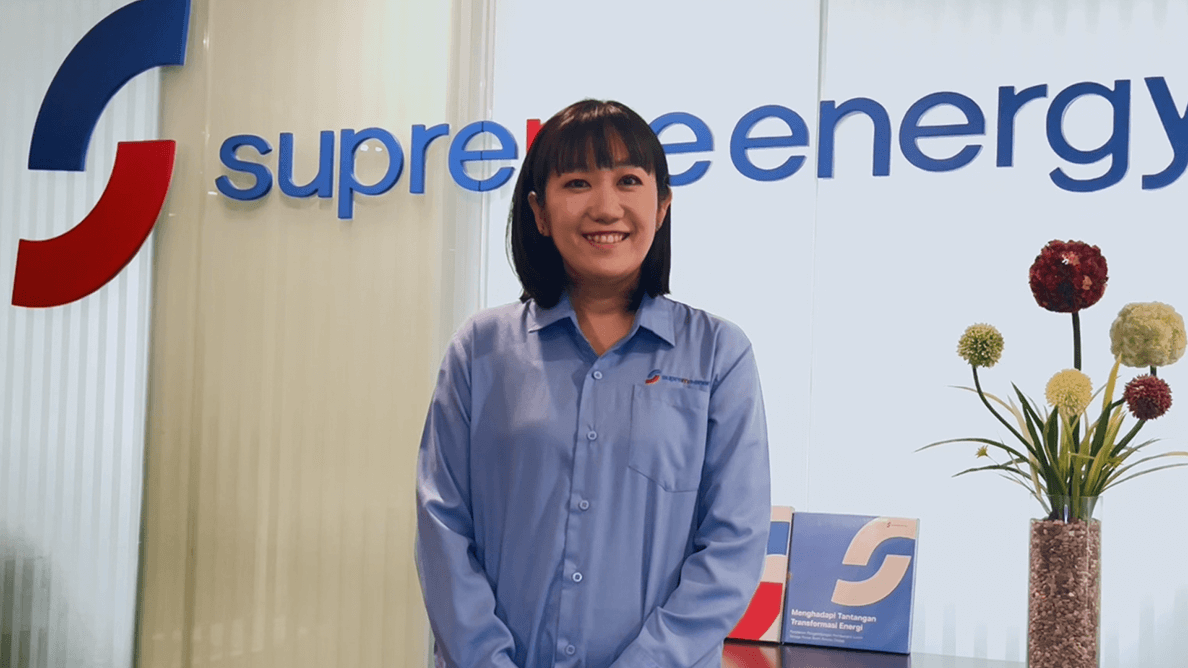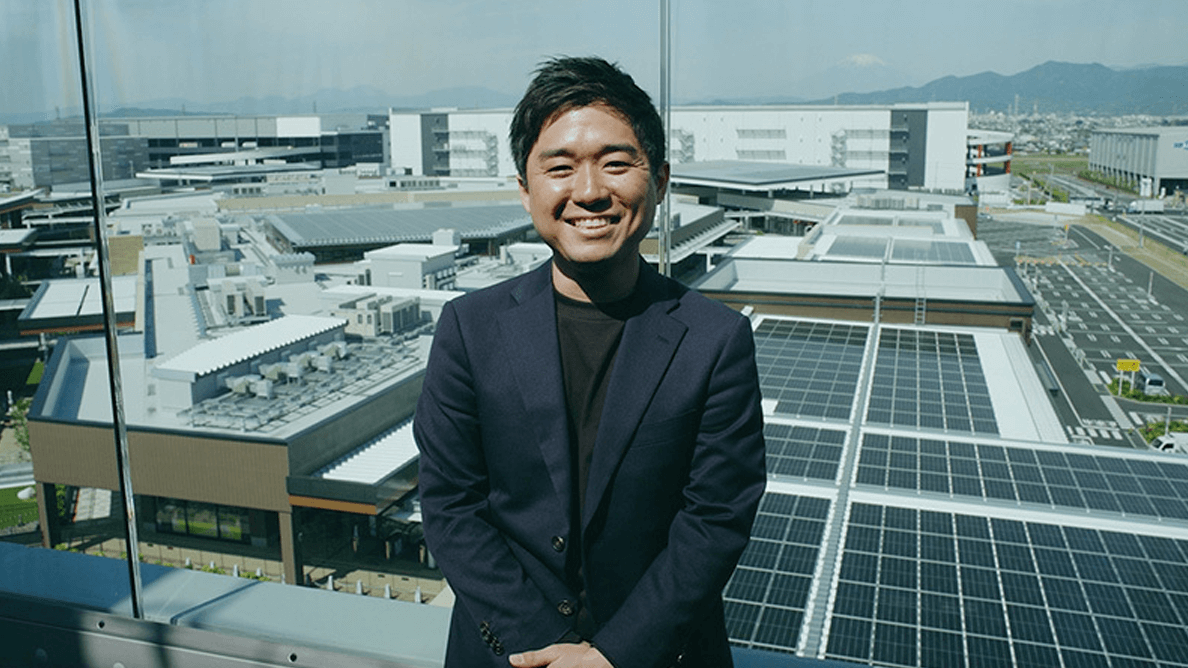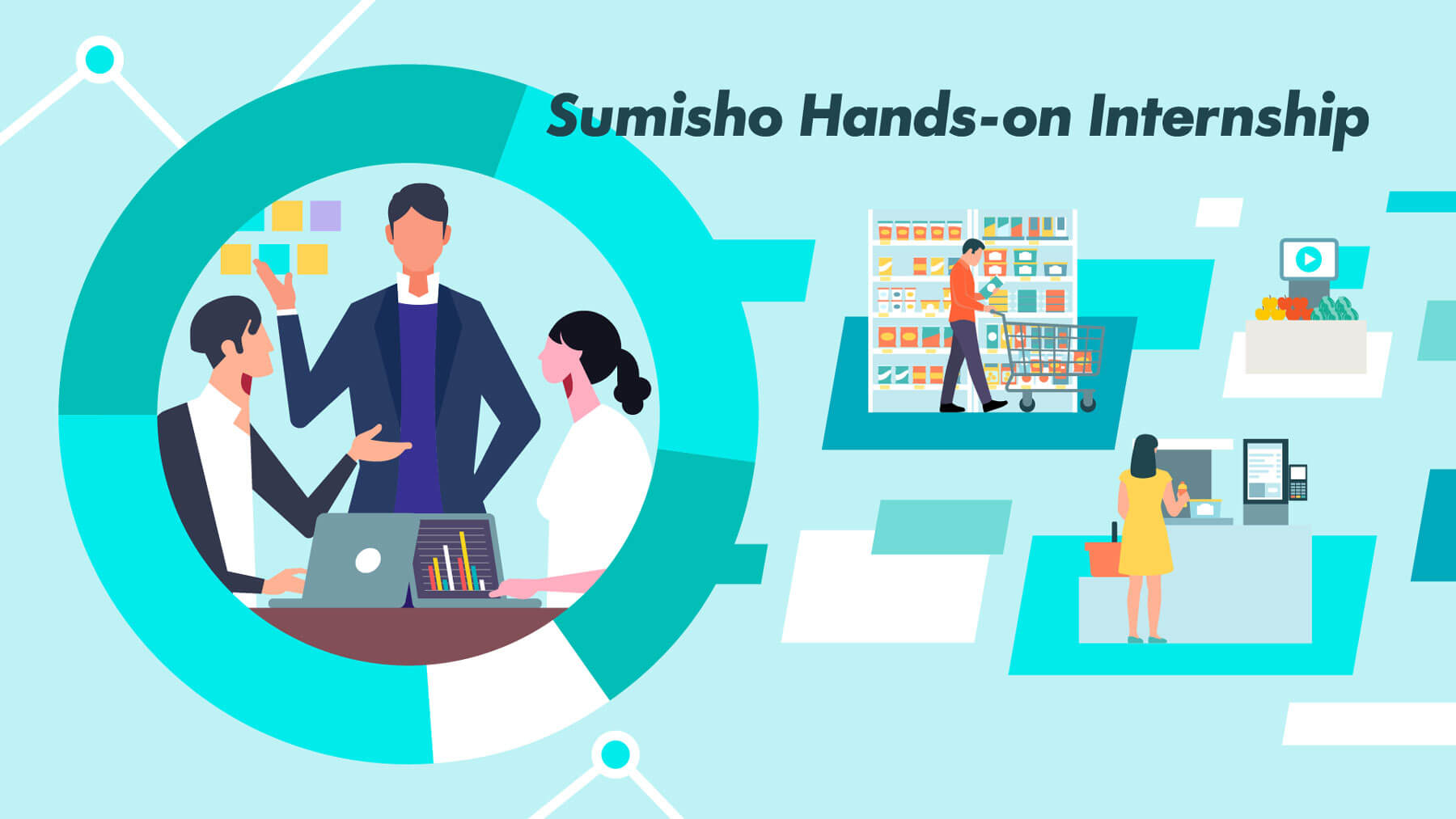- TOP
- Enriching+TOP
- 熱帯の国ガーナへ日本の伝統文化を届けに
2023.10.1
Business
熱帯の国ガーナへ日本の伝統文化を届けに

アフリカ西部、赤道付近の北緯5度から11度に位置するガーナ。住友商事は2011年にガーナの首都アクラに事務所を開設した。現在は、自動車、鋼材のトレードビジネスや、2017年の完工を目指して建設中の電力事業に携わっている。そのアクラにおいて「日本週間」が毎年実施されていることはご存じだろうか?その期間中に日本の伝統文化を紹介する一員として、アクラで過ごした8日間の様子を紹介する。
この記事は2017年1月に公開された内容です
-

制作チーム
堀江 春菜
1998年に入社し、建設不動産本部、ネットワーク事業本部、メディア事業本部(いずれも当時)を経て、2008年より広報部に所属。現在は、主に社内報や企業広告の制作を担当している。趣味は全国の秘湯巡りと、近所のスポーツクラブでの水泳。泳いだ後は、サウナの中でさまざまな年齢の人たちと井戸端会議をして日々の活力を得ている。
雨上がりのガーナで熱気に包まれた
ガーナと聞いて多くの日本人が思い浮かべるのは、チョコレートや幼いころ伝記で読んだ野口英世といったところだろうか。事実、日本でチョコレートの原料カカオ豆の輸入の約半量はガーナから(※)で、商品名に「ガーナ」とついたチョコレートが販売されていることからも、とても身近だ。現在の千円札紙幣に肖像画が使われている野口英世が、19世紀末から20世紀初頭にかけて黄熱病の研究中に最期を迎えたのも、ここガーナだったのだ。
大西洋(ギニア湾)に面したアクラを訪れた10月上旬は、ちょうど雨季と乾季が入れ替わる時期。1日のうち数時間ほど強い雨が降り、その後は強い日差しが照りつける。そのため気温は30度以上、湿度は80パーセントを上回る日々だった。空港に降り立つと、そこはまさにアフリカ。カラフルな服を身に着けた人々の喧騒と、まるでサウナの中にいるような湿り気ある熱気に一瞬のうちに包まれた。
※2015年度財務省貿易統計による

日本の心を届け続けて20年

住友商事が海外で伝統的日本文化を紹介する活動を正式に始めたのは、2015年度のミャンマーの首都ヤンゴン。世界65カ国に拠点をもつ当社が、現地コミュニティーとの良好な関係を構築する目的で実施する社会貢献活動の一環だ。
さかのぼること20年前の1995年から、当社社員の宮代江身子(環境・CSR部兼地域総括部)が、トルコやノルウェー、ウクライナなど世界各国で行ってきた個人的なボランティア活動がそのベースとなっている。現地の大学や教育機関へ出向き、デモンストレーションやワークショップ形式で日本文化に触れてもらい、日本のファンを増やし続けてきたのだ。宮代が師範免許をもつ茶道(裏千家)や生け花(草月流)のほか、書道や着付け、風呂敷包みや折り紙など、教えられるメニューは多岐にわたる。ウクライナでは計11回にわたり活動を重ねた結果、「宮代塾」と呼ばれる組織も立ち上がり、「弟子」たちが日本文化の伝承を続けているという。
そんな宮代を筆頭に、世界へ日本の心を届けたいと、私を含む女性社員4人がガーナへ渡った。
ガーナと日本の意外な共通点
最初にイベントを行ったのは、ガーナ大学日本語学科。ガーナで最も歴史が古い大学で、日本へ留学し博士号を取得した学生も多くいるという。9月から日本語を学び始めたばかりの大学院生約100人に対し、2時間の講義を行った。最初は着物を男女の学生に着付けるデモンストレーションから。単に着付けをするだけではなく、着物は季節によって生地や絵柄を使い分けることや、女性は結婚前後で袖の長さが変わること、そして結婚式には華やかな打掛けを着ることなどを説明すると、学生たちの目が一様にパッと輝いた。そしてスマートフォンでの撮影の嵐。晴れ着を着た2人のガーナ人学生や和服姿の私たちと、共に写真に納まりたいと学生たちが殺到した。

次は茶道体験。茶せんを使い滑らかな泡が立つようにお茶を点てるのは、初めての経験という学生たちだったが、自分でいれたお茶は、最後の一滴までおいしそうに飲み干していた。さらに日本から持参した食材を中心に和食の紹介をした。日本米で炊いたご飯でおにぎりを握り、海苔やしょうゆ、ワサビ、梅干し、納豆、みそ汁などと一緒に少しずつ試食してもらったところ、一様に好評で次々と学生たちの手が食材に伸びてきた。
当社のアクラ事務所に駐在している杉本俊明によると、ガーナでは小魚や干しエビで出汁をとり、調理に使う食習慣があるという。昆布やかつおで出汁をつくる日本と、直線距離にして約1万5,000キロメートル離れたガーナとの、意外な味覚の共通点を知る機会となった。

日本文化は子どもから大人まで大人気

翌日には、アクラ近郊にある幼稚園と小・中学校が一体となったインターナショナルスクールでのイベントへ参加。照りつける太陽のもと、校庭に設置されたステージを囲んで座る約1,000人の生徒たちに見つめられる中で、着付けを披露し、生け花体験や、日本のラジオ体操を一緒に行った。昔ながらのおもちゃ(けん玉や紙風船、羽根つきなど)やアニメの本を展示したところ、それまでおとなしくしていた生徒たちもとうとう我慢しきれず、ステージ付近へ大勢が一気に押し寄せ、子供たちの渦に巻き込まれてしまった。「私にも触らせて!僕にも見せて!」と、キラキラした瞳で訴えかける好奇心あふれる姿がとても印象的だった。

別の日には、当社と30年近く関係がある自動車販売会社のショールームで、さまざまな文化紹介を行った。茶道や書道のゾーンでは実際に茶せんや筆に触れてもらい、着付けや華道はデモンストレーション形式で紹介。太巻き寿司の作り方も披露し、一部の人には実際に巻いて食べてもらった。当日は、バスで訪れた近隣の小、中、高校生たちを含む総勢200人の来場者に加え、地元ガーナのテレビ局クルーも取材に訪れ大盛況だった。
ガーナに息づく日本のよさこい祭り
今回の日本文化紹介活動のフィナーレは「ガーナよさこい日本祭り」。ガーナでは15年前から毎年、この祭りが開かれている。大勢の地元の人々が訪れた会場では、学生グループや日本から訪れたチームなどが次々と、揃いの衣装で息を合わせてよさこい踊りを披露した。音楽を聞くと自然に体が動き出すリズム感やノリの良さを持つガーナの人々。キレのあるダンスは、さすがに見応えがあった。
当社が資本参加する発電プロジェクト(後述)に携わる社員やその家族は、スーパーボールすくいのブースを出し、在ガーナの日本企業らが焼き鳥やかき氷などを提供。まるで縁日のような賑わいだった。当社のブースでは書道と着付けを用意。日本から持参したうちわを半紙代わりに使う書道コーナーでは、名前を漢字で書いてあげると皆一様に喜んでいた。祭りの最後には、会場の中央で大勢の来場者が輪になって盆踊りを楽しんだ。

むせ返るような蒸し暑さの中、和服で過ごした数日間。ガーナの大地に立っていると自然とパワーが湧いてきて、どんな疲れも忘れてしまうのが不思議だった。出会った人々の笑顔によって、流れる汗を爽やかに吹き飛ばしてくれたことが思い出される。

この国の未来を共に明るく照らしたい

最後に、当社がガーナで取り組む複合火力発電事業を紹介する。このプロジェクトはアクラから約25キロメートル離れた街、テマにガーナ最大級の火力発電所(ポーン複合火力発電所。350メガワットクラス)を建設、運営するもの。2017年の完工と商業運転開始を目指してまさに今、工事が佳境を迎えている。ガーナでは経済発展に伴う電力使用量の増加もあり、恒常的に電力不足による停電がおこる。そんなガーナの一般家庭約60万世帯の電力使用量を、20年間にわたり電力供給するこの発電所は、まさに期待の星だ。
当社から現地事業会社には5人の社員が駐在、プロジェクトの進行を指揮している。建設現場周辺に住む住民を工事現場に招いたり、近くの海岸へ産卵にくるウミガメの保護活動を行うなど、地域との共生にも力を入れている。メインゾーン約5万平方メートルに及ぶ赤土の工事現場では、24時間体制で約1,300人が懸命に働いていた。ガーナの人々の毎日が、今より明るくて便利になる日も近いはずだ。

街中に溢れる人々の熱気や暖かなまなざし。「アフリカの優等生」といわれるほど民主主義が定着し治安もよく、街行く人の服装はその国民性を表すかのようにとても鮮やかで明るい。活動中、私たちはガーナからたくさんのエネルギーをもらった。そんな国の人々が日本に興味を持ち、少しでも日本を好きになり、両国の関係性と発展が今後ますます加速することを願ってやまない。