
- TOP
- Enriching+TOP
- 社会問題化していた鉄道路線が復活!マニラで挑んだ、都市鉄道再生プロジェクトの全貌
2025.5.13
Business
社会問題化していた鉄道路線が復活!マニラで挑んだ、都市鉄道再生プロジェクトの全貌

人々の暮らしと産業を支える鉄道は、都市機能と経済発展の要です。今日では環境負荷低減や駅・沿線の不動産、人流データを活用した新たなビジネスの創出といった意味でも、大きな注目を集めています。そんな鉄道関連事業は、住友商事(以下、住商)にとって最も長い歴史をもつ分野の一つ。今回は、住商が復旧を成功させたフィリピンの都市鉄道・MRT(メトロ・レール・トランジット)3号線のリハビリテーション事業について、二人のキーパーソンに話を聞きました。
-

住友商事 交通・輸送インフラ事業ユニット ユニット長
本田正規
1997年の入社後、輸送機プロジェクト部(現:交通・輸送インフラ事業ユニット)に配属。2005年よりマニラの鉄道事業に本格的に携わる。18年には、フィリピン住友商事 インフラ事業部長(在マニラ)に就任。24年4月より現職。本リハビリ事業では責任者を務める。
-
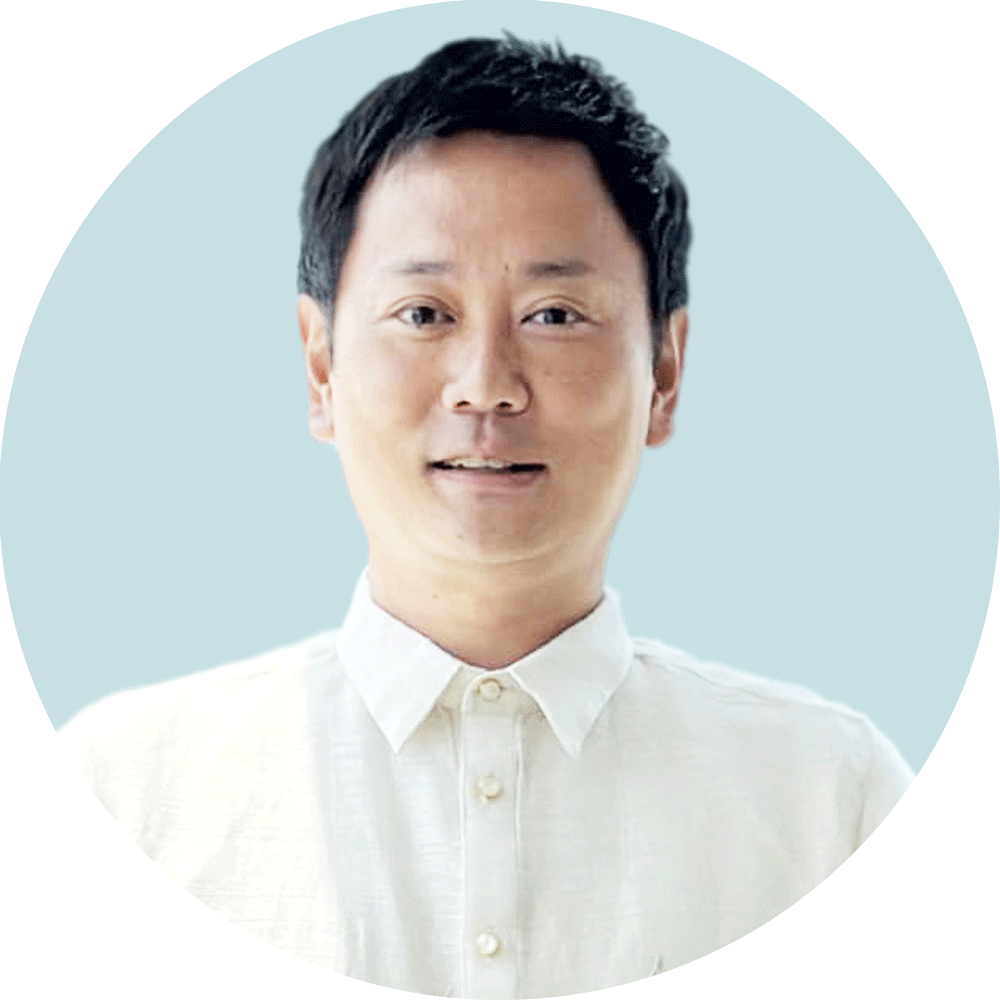
フィリピン住友商事 インフラ事業部長(在マニラ)
高橋智樹
2005年入社後、人事部に配属。08年に輸送機プロジェクト部(現:交通・輸送インフラ事業ユニット)へ異動。13〜18年までインドネシアに駐在。20年〜現在までフィリピンに駐在中。駅前開発やリテール等鉄道関連分野における事業企画・新規案件にも携わっている。

渋滞に大気汚染。新興都市にとっての鉄道網の重要性
まずは住商の鉄道事業の歩みと、現在注力しているエリアを教えてください。

本田住商では1940年代から国内メーカーの車輪や車軸の輸出を始め、50年頃から貨車や客車の輸出も行うようになりました。80年代以降は現地据え付け工事を含む鉄道システムの輸出に注力し、現在では土木構造物や線路の建設、車両・運行システムまでを一括で提供する「フルターンキー」(※)と呼ばれる案件を手がけています。さらに鉄道運営事業そのものへの投資や経営参画も行っています。
高橋現在、われわれが重点地域と位置付けているのがアジアです。アジアは人口が密集する都市が多く、さらに人口が増え続けています。脆弱な都市交通網が原因の渋滞や大気汚染、大量のCO2排出などの課題を解決するうえで、鉄道網の整備は不可欠です。
本田なかでもフィリピン・マニラ首都圏は東京23区とほぼ同じ面積ですが、人口は1.5倍の約1,400万人。2050年まで人口増加が続き、東南アジア屈指の都市圏として発展する見通しです。それにも関わらず、都市鉄道は3路線のみ。東京に80以上の路線があることを考えると、今後も大規模な鉄道整備が必要です。
※「鍵を回せばすぐに使える状態」が由来。

「スミトモに戻ってきてほしい」。社会問題化していたマニラの鉄道事情
マニラの中でも、MRT3号線とはどのような路線なのでしょうか?

高橋MRT3号線は全長17km、13駅からなり、ビジネス地区や高級住宅地を通る重要な路線です。住商は97年に三菱重工とともに、MRT3号線の土木から車両の供給、システム全般を担うフルターンキー契約を受注し、2000年に完工して営業運転を開始しました。

本田このプロジェクトは民間が主体となって建設・維持管理を行うPPP(Public Private Partnership)方式でした。でも当時のフィリピン政府の信用力は低く、支払い面のリスクから、手をあげる民間事業者がいなかったんです。そこで当時のラモス大統領の指示で住商に「スミトモでやってくれないか」と直接の依頼があったのです。他社が尻込みするなか、マニラの鉄道事業の将来性を見据えてチャレンジしたことが、その後の住商のアジアの鉄道事業における大きなアドバンテージとなりました。
18年には、MRT3号線のリハビリテーション事業を受注しています。完工からこの年まで、何があったのでしょうか?
本田MRT3号線の完工後、住商は12年間にわたり、三菱重工グループとともに同路線のメンテナンス事業を請け負っていました。しかし政権交代により突然、メンテナンス事業はフィリピンの業者にくら替えされてしまいます。その後、業者が3度も変わり、適切なメンテナンスが行われなかったため、車両やシステムはどんどん劣化していきました。運行時速は60kmから30kmに下がり、列車が駅間で停止したり、煙をあげたり。乗客が高架の上を歩く事態も頻発しました。
高橋当時、マニラ首都圏の平均通勤時間は片道3時間、往復で6時間。そんな中、MRT3号線の運行時速と運行本数が半減したため、列車内や駅は常に大混雑状態。駅での待ち時間も大幅に増え、市民の大きなストレスになっていたんです。通勤渋滞による社会的損失は、1日約60〜70億円と試算されていました。
当時、マニラの鉄道事情は大きな社会問題だったんですね。
本田政府への批判も強まったため、17年にフィリピン運輸省から「ぜひスミトモに戻ってきてほしい」と、日本政府や私どもに要請があったのです。これまでの経緯もあり、毎日の運行を続けつつ、いかにしていったん手を離れたシステムを復旧させられるか、難易度の高いプロジェクトになると感じていました。でもこの問題を解決できるのはわれわれしかいない。住商が断れば、マニラ市民はいつまでも不便でストレスの多い生活を強いられます。そこで当時、日本にいた私がフィリピンに駐在し、三菱重工のエンジニアと現地調査を行い、問題点を洗い出し、リハビリ工事の計画を策定しました。日本政府の全面的なバックアップのもと、通常なら複数年かかる円借款の組成を異例の1年弱で終え、18年末に契約締結に至ることができました。
コロナ禍真っただ中のリハビリ工事。市民や政府の思いに応えるために
リハビリ事業は順調に進んだのでしょうか?
本田いえ、20年に新型コロナウイルスの感染が拡大し、三菱重工の日本人社員は全員帰国せざるを得なくなりました。私一人がマニラに残り、三菱重工の方が日本からリモートで現場作業員を管理、監督しましたが、工事の進捗スピードへの影響は避けられませんでした。そんなある時、フィリピン側の責任者から呼び出されました。叱責を覚悟して伺うと、「よく残ってくれた。こちらも全面的に支援する」と涙ながらに感謝されたのです。エッセンシャルワーカーの足であるMRT3号線は絶対に止めないよう運輸大臣から厳命されているなか、頼みの綱の日本人が帰国してしまい、責任者も不安だったのだと思います。それでも私を信じ、励ましてくれた彼に応えたい。そんな思いで関係者一同が奮起し、21年末に予定より6カ月も早く、工事を完了することができました。


高橋リハビリ工事は鉄道の運行終了から始発までの数時間で集中的に行う必要があります。事前の綿密な段取りが重要で、想定外の出来事にも迅速に対応しなくてはなりません。例えば、工事を発注している下請け企業が資金ショートを起こして経営難に陥り、業務の継続が難しくなった。お客さまとのコミュニケーションの食い違いからクレームを受けている。そのような技術面以外の問題が噴出する度に、打開策を考えることも、私どもの重要な役割でした。安全面に配慮しながら、期限内に工事を終わらせなくてはならないというプレッシャーは、とても大きなものでしたね。
本田リハビリ工事が完了した後も、車両内でぼやが発生したり、信号機器の不具合で列車が止まったり。これらはシステムの設計寿命や耐用年数が原因で、私どもにはどうすることもできない面もありました。とはいえ、このプロジェクトは市民からの期待が大きいだけに、問題があるとメディアやSNSで政府が批判されます。そこで住商が、ネガティブな面も含め、誠実・丁寧に情報開示を行い、説明責任を果たす必要がありましたね。

工事完了後、市民や政府からの反響はいかがでしたか?
高橋20年に年間3,100万人だったMRT3号線の利用者数は、24年には4倍以上の1億3,500万人になりました。日本の鉄道技術により、マニラの渋滞や混雑、環境悪化を改善でき、人々の暮らしが向上したことは本当にうれしいです。市民からは「通勤時間が短くなり、家を早く出ずに済むようになった」「3号線はエアコンがよく効いていて最高だ」との喜びの声をたくさんいただきました。
本田「スミトモは一番大変で危機的な状況を救ってくれた」とフィリピン政府や運輸省から感謝の言葉をいただいた時は、これまでの苦労がむくわれたと思いました。このプロジェクトで強固になった信頼関係が、その後のメンテナンス契約の延長、他路線の事業参画、新規大規模プロジェクトへの車両供給など、新たな受注につながりましたね。
高橋住商は20年にLRT1号線事業の株式を購入し、経営に参画しました。日本で顧客満足度が極めて高い阪急電鉄と、長らくマニラ首都圏の鉄道整備を支援してきたJICAに協力いただき、より快適な鉄道サービスを追求しています。さらに現在、民営化を予定しているMRT3号線の経営参画についても、フィリピン政府と協議しています。今後は既存の鉄道路線だけでなく、新たに駅前開発など周辺領域にもビジネスを拡大し、マニラという都市の利便性をさらに高めていきたいと考えています。
培ってきた技術やサービスを各国へ。商社だからこその鉄道ビジネス
住商の鉄道事業は、この先どのような展開を目指しているのでしょうすか?

本田24年にはイギリス・ロンドンの地下鉄「エリザベス・ライン」の運営事業を現地鉄道事業者The Go-Ahead Groupおよび東京メトロと受注し、25年5月から運営を始めます。今後の注力エリアとしては、日本の鉄道システムが複数建設される予定のバングラデシュを筆頭に、鉄道需要が大きい東南アジアが挙げられます。さらに、長年ビジネスを継続している北米でも、貨物鉄道への進出を検討・計画しています。
高橋日本の鉄道は信頼性が高いだけでなく、新幹線や空港アクセス線、上下分離による民営化などの世界初の取り組み、沿線エリアと一体化した街づくりなど、世界に類を見ないユニークな強みをもっています。優れた鉄道技術やサービスを、長年、グローバルなビジネスで培ってきた私どものノウハウやネットワークを活用しながら、世界に広げていきたいですね。
本田現在、日本の鉄道事業者は駅ナカ・駅ソトの不動産、交通決済から派生した金融業、広告やリテールなど、収益の半分以上を運輸事業以外で稼いでいます。私たちも、鉄道と絡む不動産開発、人流データを活用したDXなど、他部署とも連携しながら多角展開を目指します。何より、培ってきた鉄道インフラや乗客へのアプローチ機会を最大限に活用し、その国や地域のニーズをくみとった新しいビジネスを創出することこそが、商社であるわれわれのミッションだと考えています。
























