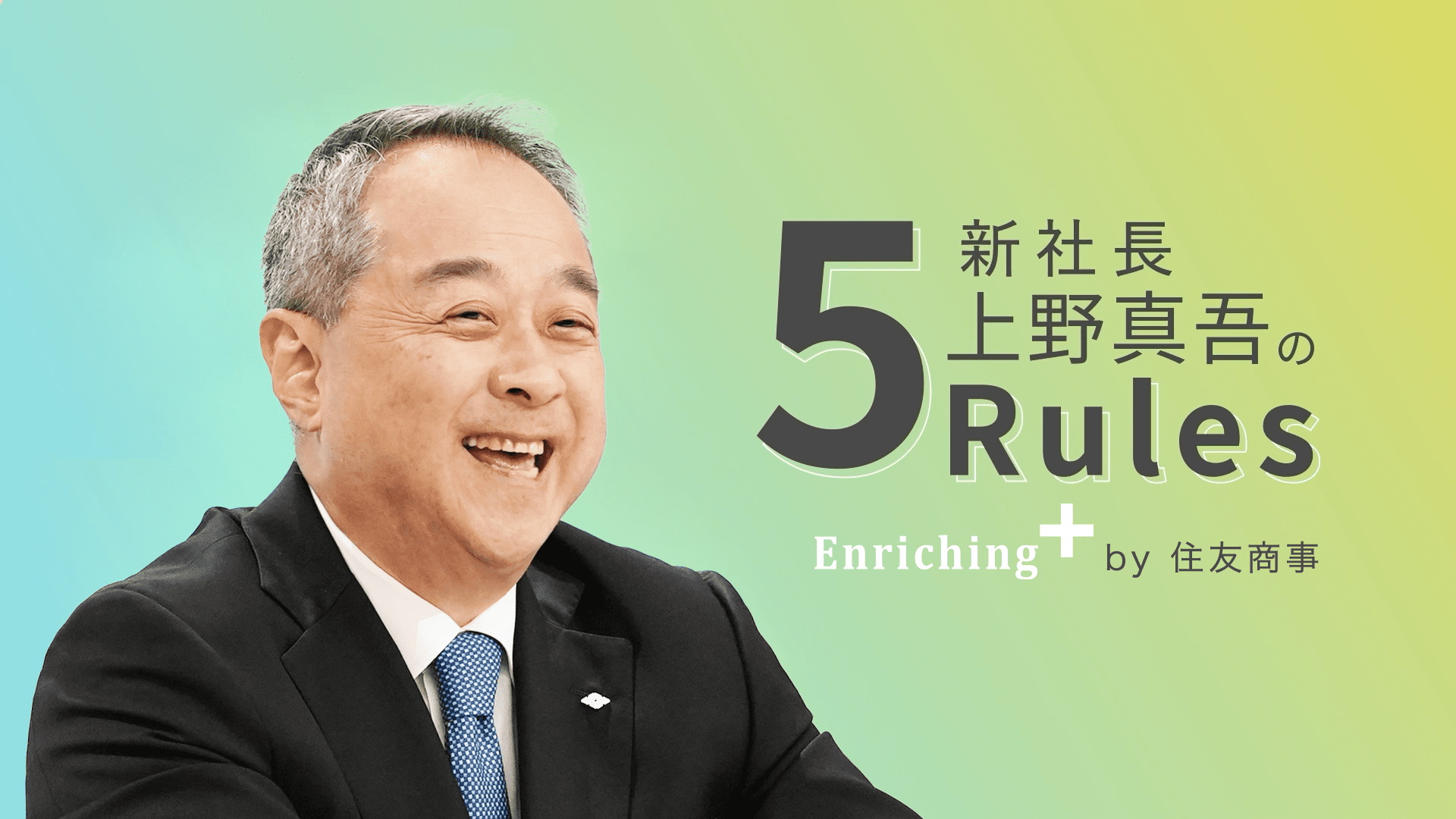- TOP
- Enriching+TOP
- 世界で日本の価値を高めたい。20代で起業した住商アルムナイが語る、「ゴールドリブン」のキャリア形成
2025.11.10
Culture
世界で日本の価値を高めたい。20代で起業した住商アルムナイが語る、「ゴールドリブン」のキャリア形成

住友商事(以下、住商)を退職後、別のフィールドで活躍するアルムナイ社員(=OB・OG/※1)にスポットを当てる本企画。今回は、入社3年の2016年に住商を退職し、その後「知識のシェアリングサービス」を手掛けるグローバルスタートアップ・アーチーズ株式会社を設立した加藤洋気さんにインタビュー。「どうすれば世界で日本の価値を高められるか」という大志を抱き続ける加藤さんが、20代のうちからどのようにキャリア形成を図ってきたかに迫ります。
-

アーチーズ CEO
加藤 洋気
2013年住友商事に新卒入社し、米国のエネルギー投資プロジェクトや新規事業開発などを担当。16年にコンサルティングファームのYCPに転職し、ベトナム拠点の立ち上げなどに携わる。19年にアーチーズを設立。世界8拠点、250人の社員を抱え、各国を飛び回る日々を送る。
社会的意義を感じるスケールの大きな仕事に携わった住商時代
まずは、住商に入社した理由を教えてください。
私はもともと父が官僚、兄たちが政府系金融と商社勤めだったこともあり、学生時代から「我が国産業がどうあるべきか、海外でどう勝つべきか」といった会話が自然とあるような家庭に育ちました。当時から海外に行ってトヨタやソニーを見るとうれしかったですし、ライフミッションとして「世界における日本の経済的プレゼンスの維持に貢献したい」と考えるようになりました。就職活動の際も、「日本に貢献できる企業」「自分が実際に活躍できる企業」の二つを軸にしていたんです。
前者の観点ですと、メーカーや金融、コンサル、さらには政府系機関にも興味はありましたが、総合商社を選んだのは、プロダクトや技術を持たず「人」で勝負しているところに文系で専門性のない自分でも活躍の可能性を感じたから。特に住商は日本を支える財閥系の一角でありながら、人柄の良さを感じる企業風土で、自分にも合っていると思いました。

住商ではどのような仕事をしていたのでしょうか?

最初は米国のシェールガスのサプライチェーンにおける上流権益の投資・管理チームに所属していました。日本にとっても重要な資源の確保につながる、社会的意義を感じられるような巨大なビジネスプロセスの一端に関われたのは、やりがいやワクワク感がありましたね。
2年目からは、新規事業の開発担当に。自分がイニシアチブを取ってプロジェクトに取り組めた部分も多く、社内外の関係者と組んでビジネスの構想から顧客への営業を実施したり、海外出張に行く機会もいただいたりと、グローバルなビジネスマンになる上で大きな成長の糧になりました。
順風満帆にも見えますが、入社3年で退職を決意された理由は何だったのでしょうか?
退職を決意したのは、大きな組織で自分が大きくなるよりも、小さな組織を自分の手で大きくしていく方が、早いし成長もあるしリターンも大きいのではないか、と思ったからです。住商は若手にも素晴らしい環境を提供してくれる会社でしたが、一方で高度に仕組み化された事業をいくつも持つ大きな組織で、自分がその仕組みを変えたりつくったりできる立場になるにはどうしても時間がかかる。野心家で生き急ぐタイプの私は、最初は小さくても、仕組みをゼロから生み出せるビジネスパーソンになりたいと思いましたし、今の時代はスタートアップでもテクノロジーや資金や人を集めて、それをスケールさせることができると思ったんです。
転職先には、コンサルの経験を積みつつスタートアップの成長を学べるYCPを選びました。YCPは、大学時代にインターンとしてお世話になった企業で、創業社長のことをとても尊敬していたので、彼が起業した29歳までに自分も起業したいとも考えていたんです。
事業と組織づくりで挑むアーチーズ。根底には住商の「浮利を追わず」の精神
実際に20代最後の年にアーチーズを創業していますが、事業内容を教えてください。
端的には、「人の知見を企業につなぐ、グローバルな知見シェアリングプラットフォーム」を提供しています。企業が求めるピンポイントな知見を有しているエキスパートとのマッチングサービスで、主に1時間のインタビューを通じて、その知見をヒアリングしていただけます。
もともと日本以外にも東南アジアや中国、韓国など、言語の壁などから状況が見えにくいアジア市場の知見をつなぐことから始めて、今はイノベーションの中心である米国市場もカバーしています。AIが提供できない知見の獲得手法として、住商をはじめとする総合商社の方々にもたくさん利用いただいていますね。
現在のアーチーズは、14カ国・250人のメンバーが集う多国籍チームへと成長中です。互いの違いを尊重しながら成果を出すカルチャーを育み、国境や文化を越えた協働が日常となっています。社内では、入社から半年でマネージャーに抜擢される20代メンバーがいるなど、若手がスピード感をもって挑戦・成長できる環境を意識的につくっています。


住商時代の経験で、現在の事業に生きていることがあれば教えてください。

私が住商にいた短い期間で培ったものは、スキルよりもマインドセットの部分が大きかったと感じています。特に影響を受けたのは、住商の根底にある「浮利を追わず」という事業精神です。自営業やスタートアップはつい目先の数字を追いがちですが、住商社員は短期的な利益を追うのではなく、社会に貢献して価値創造をしていく「大義」が自然と根づいていたことに、外に出て改めて気付きました。
優秀な人材や投資家を巻き込み、事業を大きくしていくためには「社会を変えるビジョン」や「長期的な価値創造」が不可欠です。そのため、キャリアの初期からこうした精神を持てたことは、自分にとって大きな財産だったと感じています。
あとは、日本を代表するような大企業がどのように意思決定してビジネスを動かしているのかを理解できたことも、アーチーズが大企業とパートナーシップを築く際、すごく意味がありました。
住商にいたことで、目線が自然と上がったのですね。
そうですね。私を起業家として社会に貢献していて立派だと言ってくださる方もいますが、アーチーズが生み出している付加価値なんてまだ2桁億円前半。一方で総合商社の課長や部長級の方々は数百・数千億円の事業をいくつもつくっている方たち。住商を飛び出したからには、「住商の同年代やそれより上の方たちに負けない価値を社会に生み出さないと」というプレッシャーを感じています。
「ゴールドリブン」の思考法が、自律したキャリア形成につながる
加藤さんが今後成し遂げたいことを教えてください。
私は学生時代から一貫して「どうすれば、世界で日本の価値を高められるか」というパッションを抱いています。そのために、アーチーズを立ち上げ、「知見の民主化」を事業として進めていますが、いずれはAIと人間の知見を組み合わせて、企業の正しい意思決定を支援する仕組みを、業界や地域の垣根を超えてグローバルに展開したいと考えています。そして将来的には、事業の経験を生かして、日本の政策や国政にも関われたらと思っています。

住商では、まさに加藤さんのように早い段階から自律的なキャリアをデザインしていくことを促していますが、キャリアに悩む若手社会人へアドバイスをいただけますか。
一番伝えたいのは、「ゴールドリブンでいきましょう」ということ。私自身、学生時代から自分が人生を懸けて成し遂げたいことを考え続けていますし、そこから逆算する形でキャリア選択をしてきました。こういったゴールが明確であれば、日々安定したモチベーションが生まれますし、周囲の人も巻き込みやすくなり、より大きなアウトプットを出しやすくなると思います。
そのためにまずは、「自分のライフミッションは何なのか」を言語化してみることが大切です。それは将来変わってもいいですし、最初は強い想いを持ちきれなくてもいい。でもそういった人生のミッションやそれに向けた毎年のゴールを仮設定すること、それを考え続け、育てていくことが大事だと思います。
時々、住商にいる方からキャリアについて相談を受けることがありますが、人によってゴールが違うから、一概に「どの道に進むべき」とも言えません。ただ、個人的にはほとんどの場合が「住商にいる方がいいのでは」と感じます。結局会社は、自己実現のための、社会に付加価値を効率的に生み出すための手段であり、一つの企業、特に十全なビジネスインフラを持ち、大きな社会的インパクトを生み出せる商社でキャリアを築いていく強みや魅力は、本来大きいはずです。
私の場合は、自らのゴールに向かって起業という選択をしましたが、ただ「今やっていることが嫌だから」とか「不満があるから」で辞めた人はどこに行っても成功しないと思います。きちんとゴールを定義して、頑張った結果それでも合わないのであれば、そのゴールを変えるか、あるいは手段を変えるか……つまり社内で変革を続けていくのか、社外の新しい環境でチャレンジするのかなど検討していけばいいと思います。
最後に、加藤さんがキャリア形成で大事にしていることを教えてください。
キャリアの本質は、何の経験やスキルを得られるかのインプットや給与・待遇ではなく、「どれだけ社会的価値を最大化できるか」というアウトプットで決まります。自分のライフミッションに対して「アウトプットドリブン」で行動し、必要に応じてゴールとアプローチを調整するサイクルを繰り返すことが成長と成果につながる。私はそう考えています。
どんな道を選んだとしても、そこでしっかりと価値を発揮できれば、評価と報酬は後から自然とついてくるはずです。それが仕事へのやりがいや自己実現につながり、ひいては豊かな人生を歩むきっかけになるのではないでしょうか。