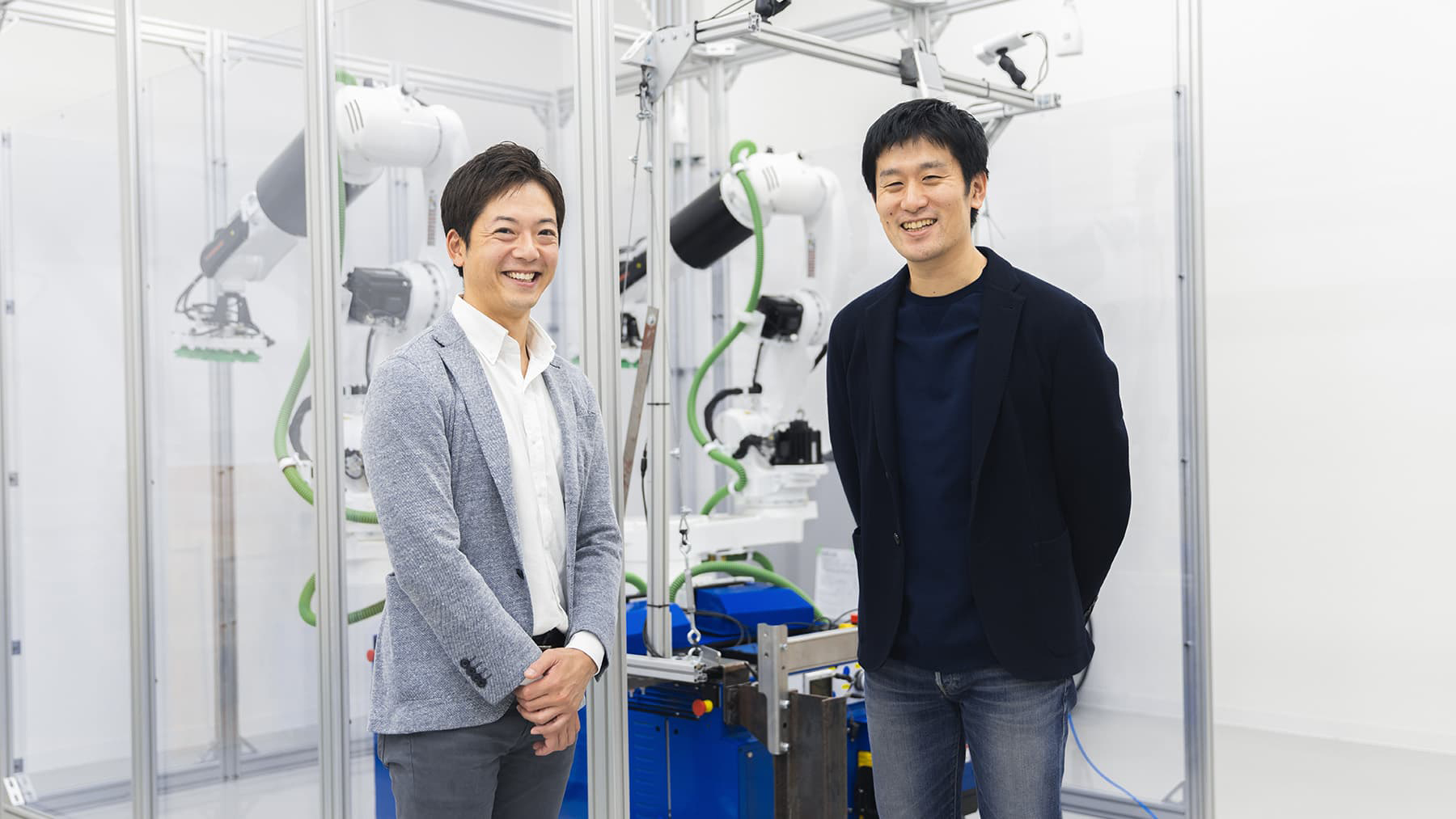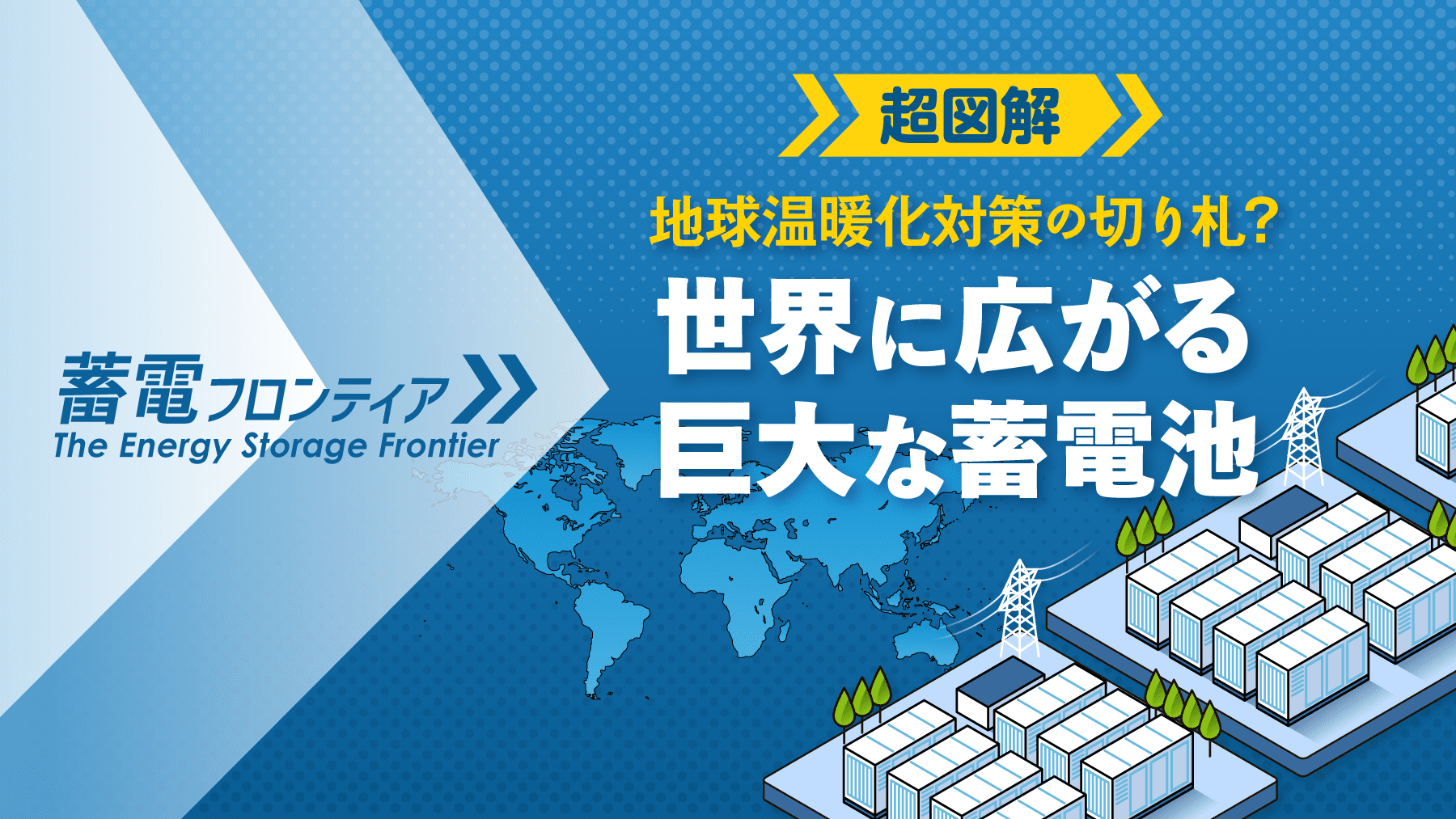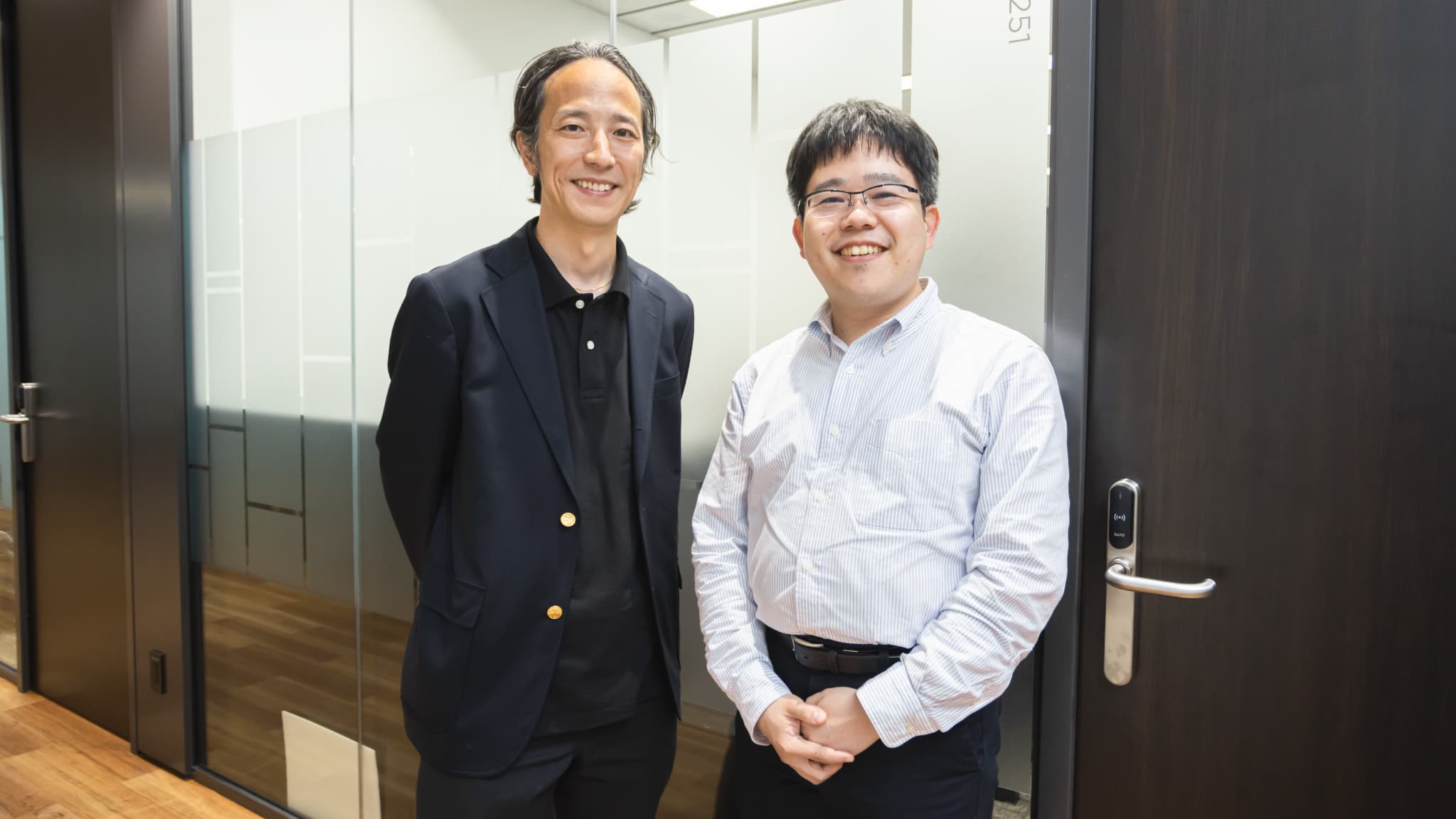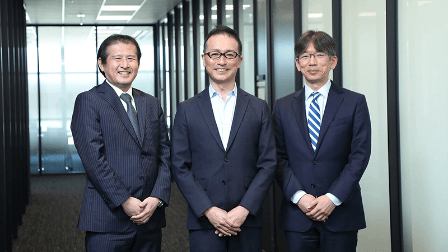- TOP
- Enriching+TOP
- 「理系女子は特別じゃない」スタンフォード大生・松本杏奈が見つめる、バイアスのない未来/E+特別編「ISSUE」
2025.3.28
+ (Plus)
「理系女子は特別じゃない」スタンフォード大生・松本杏奈が見つめる、バイアスのない未来/E+特別編「ISSUE」

「理系は男子向き」という周囲の声に惑わされずに、スタンフォード大学工学部に進学した松本杏奈さん。渡米して目にしたのは、女子学生が全体の約半数を占める教室風景でした。
日本では少数派とされる理系女子が、なぜアメリカでは活躍できるのでしょうか。
今回Enriching+特別編「ISSUE」として、松本さんにインタビュー。彼女の経験をもとにアンコンシャスバイアス(※1)の乗り越え方を探り、誰もが自由に夢を追いかけられる未来の可能性を考えます。
※1 過去の経験や知識、価値観をもとに発生する無意識の思い込みのこと
-

松本 杏奈
2003年生まれ、徳島県出身。2021年9月、米・スタンフォード大学に進学。工学部で、プロダクトデザインの考え方や手法を学ぶPhysical Design+Manufacturingを専攻。「誰も取り残さない社会と技術と芸術を。」をモットーに、コミュニケーションにおける障壁の克服を目指している。柳井正財団5期生。学業と並行し、アーティストとして創作活動も行う。

「工学も芸術も手放したくない」。アメリカ進学を決断した理由
アメリカでの生活が4年目に入ったそうですが、最近はどのように過ごされていますか?
松本私は今、スタンフォード大学の工学部4年生で、「Physical Design+Manufacturing(※2)」を専攻しているのですが、本当に充実していて、めちゃくちゃ忙しくしています(笑)。
授業や研究だけでなく、自主的にいろいろなプログラムに参加したり、新しいプロジェクトを立ち上げてアウトプットをつくったりしているので、毎日やることが盛りだくさんな日々を過ごしていますね。
※2 機械工学を基礎とし、ヒューマンセンターデザイン等を主にした物理プロダクトデザインを学ぶ専攻
松本さんのSNSを拝見しても、充実した学生生活であることが伝わってきます。あらためてですが、スタンフォード大学への進学を決めたきっかけは何だったのでしょうか?
松本一番のきっかけは、入学試験の面接でした。面接官との会話が弾み、自分がスタンフォードで学んでいる未来をイメージできたんです。それが決め手となって進学を決めました。

そもそも、なぜアメリカの大学を目指そうと思ったのですか?

松本理由は意外と単純で、アメリカの大学ではプロジェクトベースかつ、ディスカッション形式の授業が多いと知り、それに憧れたからです。それに詳しく調べてみると、アメリカでは理系の学生でも芸術や音楽といった文系の活動に注力できることを知りました。
私はアーティストとして作品作りを続けていて、それを大学進学後も辞めたくはありませんでした。工学か芸術かという二者択一でなく、どちらも続けて融合できる環境があることに感動し、「自分にとって最適な学びの場はここだ」と確信しました。それが、アメリカの大学に進学を決めた理由です。
クラスの半分を占める理系の女性。スタンフォードが示す新たな「常識」
日本の大学では、工学部に通う女子学生は非常に少ない印象です。スタンフォード大学ではいかがですか?
松本女子学生も女性研究者も本当に多いですね。工学部の授業に行くと約半分が女性で、女性教授も当たり前のようにいて、日本とは異なる世界に最初は驚きました。
でも、よく考えてみると、女性と工学ってじつは親和性があると思うんです。たとえば、小さなころに女の子がやる指輪づくりやネックレス作り。これって、本質的には機械工学でやっていることと同じなんですよね。シルバーアクセサリー加工の授業すらあるし。だから、女子が工学部などの理系学部で学びたいと思うのはごく自然なことなのに、日本では理系の研究プログラムに参加しても女子は私一人、なんてことがよくありました。

日本で女性の理系進学者が少ない理由は、どこにあると思いますか?
松本一番大きいのは、大人が無意識に持っている偏見、つまりアンコンシャスバイアスの影響だと思います。日本では、女子が「理系に進学したい」と宣言すると、周囲からめずらしいと思われることが多いです。私も高校時代に、「理系は体力勝負だから、男子のほうが向いている」とか「女子が工学部に行ってどうするん?」といった言葉を何度も投げかけられました。
それは大変だったでしょうね。
松本周囲からの言葉は、言った本人が思っている以上に強いパワーを持ちます。否定的な言葉を繰り返し浴びるうちに、自分の進みたい道を諦めてしまう女子がいるのも無理はないです。実際、私の友だちもまわりからの言葉によって、泣きながら工学部から他学部へと進路変更をした子がいました。

こうしたエピソードを「アジアサイエンスキャンプ(※3)」で知り合った東京の高校に通う友達に相談すると、「いつの時代の話?」と驚かれたことがありました。日本でも場所によって教育の環境に違いがあるものの、やりたいことが明確にあるのに、それを実現する道が断たれてしまうのは、大きな問題です。
※3 アジア地域の高校生・大学生を対象にし、研究者や技術者から直接指導を受けられる科学技術体験合宿プログラム
松本さらに日本では、教科書や進学情報サイトを含めたメディアのコンテンツの中にもジェンダーバイアスが根深く存在していると思います。例えば、職業について調べると、自動車整備士は男性、幼稚園の先生は女性として紹介されるケースが多いですよね。本来は自由なはずなのに、ジェンターによって役割が決まっているかのように見える描写が、子どもたちの将来に大きな影響を与えてしまっていると感じます。
私がメディアに出て声を上げようと思ったのも、こうした固定されたイメージを変えるためです。私のような今はまだイレギュラーな存在を知ってもらうことで、少しずつ社会も変わると思うし、それによって学生たちの選択肢を広げられると思っています。
思い込みの壁を壊す。アンコンシャスバイアス解消のヒント
アメリカで暮らす中で、アンコンシャスバイアスに対する意識や対応に、日米間の違いを感じることはありますか?
松本日本とアメリカでは、アンコンシャスバイアスへの意識の差を感じますね。大学のあるカリフォルニアでは、人種や性別などによる差別・偏見をなくそうという共通認識が広く共有されていて、人のバックグラウンドに関する発言に対しては非常に敏感です。
たとえば「女の子なのに〇〇」「男の子なのに〇〇」と口にする人がいたとすれば、周囲からは「この人ヤバいな」と思われます。「日本人だから〇〇が得意なんだね」みたいな発言も、人種差別的な観点であまり良いとされない。
こういった認識はカリフォルニアが先進的だからなのかと思っていたましたが、2023年にホームステイしたフロリダの田舎町でも同じでした。老夫婦に工学部で学んでいると話すと、皆さん「かっこいい!」とポジティブな反応をしてくれました。でも、日本では「女の子がどうして?」や「え、あなたが?」といった反応を受けることもあり、社会に根づくジェンダーロール(※4)の影響を感じます。
※4 性別によって期待される役割や行動のこと

なるほど。日本とアメリカでは状況が大きく違うんですね。
松本そもそも「リケジョ」や「イクメン」という言葉が存在していること自体が、アンコンシャスバイアスが残っている証拠だと思います。理系で活躍する女性や育児をする男性が特別視されるからこそ、わざわざ名前がつけられているわけで、こうした言葉がある限り日本は変わらない。本来はそれらが特別視されない社会を目指すべきです。
最近では、日本の理系大学や学部に女子枠が設けられるようになりましたが、これは非常に良い取り組みだと感じています。それまで女性の進学者が少なかった学部に女子枠ができることで、新たにチャレンジしようと思う子が現れて、徐々に女子学生の増加につながっていくはず。0よりはよっぽどマシ。女子枠の設置に対しては反感の声も多いですが、私は正直「男子しかおらん内輪の中で学んで、何が楽しいん?」と思います。いろんなバックグラウンドの仲間と出会って切磋琢磨するからこそ、成長できるんじゃないでしょうか。

日本では大学に限らず、社会のさまざまな場所で「女性枠」のような制度が設けられると、SNSなどで炎上することが少なくありません。しかし、これまで男性中心でつくられてきた社会制度の中で、女性が機会を損失してきたという歴史に目を向けず、「女性だけを優遇するのは不公平だ」と批判する人が減らない限り、日本でアンコンシャスバイアスを解消するのは難しいのではないかと感じています。
好きなことをする自由が社会を変える
そうした社会の意識を変えていくためには、何が必要だと思いますか?
松本日本では、「誰もが自分の人生を好きなように生きていい」という認識がまだ十分に広がっていないと感じます。人の選択に干渉したり、その決断に否定的な意見を伝えたりすることも見られますが、アメリカではそういう行動をすると、「None of your business!(あなたには関係ない)」として、一蹴されるのが当たり前です。
アメリカで実感したのは、自分の人生をしっかり生きている人ほど、他人の人生を尊重する傾向が強いということです。日本でももっと一人ひとりが自分の好きなことをして、自由に挑戦できるようになれば、お互いを尊重し合える社会が実現し、アンコンシャスバイアスも減らせるのではないかと思います。

なるほど。とても興味深いお話ですね。一方で、松本さんのように好きなことややりたいことが見つけられないという方もいると思いますが、どうすればいいでしょうか?
松本まずは、自分を知ることが大切だと思います。私は少しケチな性格なので(笑)、限られた時間の中でもできるだけ多くの人と出会い、美味しいものを食べて、面白いことをたくさん経験したいと考えています。
人生でフッ軽に動ける時間を50年と仮定すると、意外と残された時間は少ないんですよね。そのため、自分が「楽しい」「得意だ」と思えることを見つけ、最良の選択をして進む方が、きっと人生がより楽しくなると思っています。
最後に、アンコンシャスバイアスを減らし、誰もが自分らしく生きられる社会を実現するために、私たちが日々できることを教えてください。
松本繰り返しになりますが、まずは自分の人生を好きなように生きること。これは、若い世代だけでなく、上の世代もそう。若者たちの選択や決断は、親や先生、上司といった上の世代にかかっています。誰もが「私の世代はこうだったから下の世代も同じであるべき」と考えてしまいがちですが、今は時代が異なるので、上の方たちも古い価値観に縛られずに寛容な姿勢であることです。
また、「○○なのに」といったバイアスがかかった発言を一切しないことも重要です。自分でそういう言葉を口にすると、 それがネガティブな自己暗示につながるので。まずは自分に対して「〇〇なのに」と思うのをやめることから始めてください。そうすることで、自然と他人に対しても偏見を持たなくなり、結果的に周囲への圧力が減っていくはず。
こうした世代を超えた意識の変化が、日本全体の社会を前向きに変えていく力になるのではないでしょうか。
Enriching+では、世の中の課題やトレンドに着目し、新しい価値を提示することで、私たち一人ひとりの考えるきっかけとなるようなコンテンツ「ISSUE」を制作・発信しています。
ジェンダーバイアスが教育やキャリアの選択に影響を与えることで、多くの才能が正当に評価されず、社会全体の成長を妨げるリスクがあります。 本企画では、多様な人材が活躍できる社会を目指す意図を込め、松本杏奈さんと一緒にバイアスを乗り越える方法や多様性を受け入れる未来の重要性を考えました。
住友商事グループは、属性や従来の価値観にとらわれず、多様な個々人がそれぞれの力を最大限に発揮し、新たな価値や革新を生み出し続ける環境づくり、Diversityを活かす文化・意識の醸成を進めています。