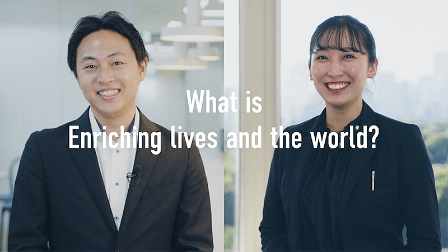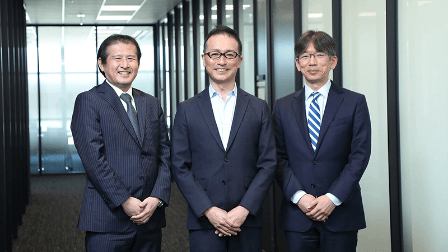- TOP
- Enriching+TOP
- 住商がマレーシアで地域医療を支える。国内No.1のクリニックになるまで
2024.12.3
Business
住商がマレーシアで地域医療を支える。国内No.1のクリニックになるまで

小売事業やドラッグストア・調剤薬局事業で培った知見を生かし、住友商事(以下、住商)は、2020年に東南アジアの民間医療・クリニック事業に本格参入しました。最初に参入したマレーシアでは、4年間でクリニック数を100以上増やすなど、同国No.1の事業規模を誇るまで成長しています。住商としては未知の領域であったクリニック事業をどのように拡大させてきたのか。担当者2名が明かしました。
-

海外ヘルスケアユニット 事業開発第二チーム チームリーダー
磯部 昌宏
2006年入社。リスクマネジメント業務や事業会社での経営企画等を担当。米国留学を経て18年よりヘルスケア関連の事業開発に従事。19年から24年までマレーシアに駐在し、主にマネージドケア事業や新規事業開発を担当。24年7月より現職。
-

Chief Operating Officer, CareClinics Healthcare Services Sdn Bhd
川副 亮
2003年入社。デジタル関連サービスの企画開発・営業に従事。米国でのベンチャー投資業務を経て、E コマース事業の海外事業開発・投資管理業務を担当。18年よりヘルスケア関連の事業開発に従事し、20年より現職。

めざましい経済成長を遂げるマレーシアでヘルスケア事業に挑む意義
東南アジアの中でも、先んじてマレーシアでクリニック事業に参入した理由は何ですか?
磯部 まず、東南アジアでは、生活習慣病の増加などを背景に医療サービスの質の向上や医療費上昇の課題があり、病気の重篤化を防ぐ健康管理や「かかりつけ医」の機能、いわゆる「プライマリケア」のニーズが高まっています。一方で、これらの医療課題に対して、医療サービスの質が不十分な現状があります。そこで、地域のクリニックを支援し、サービスの質を引き上げることで、高まる医療ニーズに応えたいと考えました。
マレーシアは経済の発展でいえば1人当たりの名目GDPは1万ドルを超えており、周辺諸国と比較し一定の成熟がありつつ引き続き堅調に成長しています。また、先行して展開し、既に300万人ほどの会員がいるマネージドケア事業(※)との相乗効果で、より良い医療サービスが提供できると考えたことも、事業拡大の理由の一つです。
※主に公的医療制度が充実していない国で発展しつつある管理医療システムで企業・民間医療保険会社、マネージドケア事業者、医療機関の三者が連携して医療サービスを提供する仕組み。
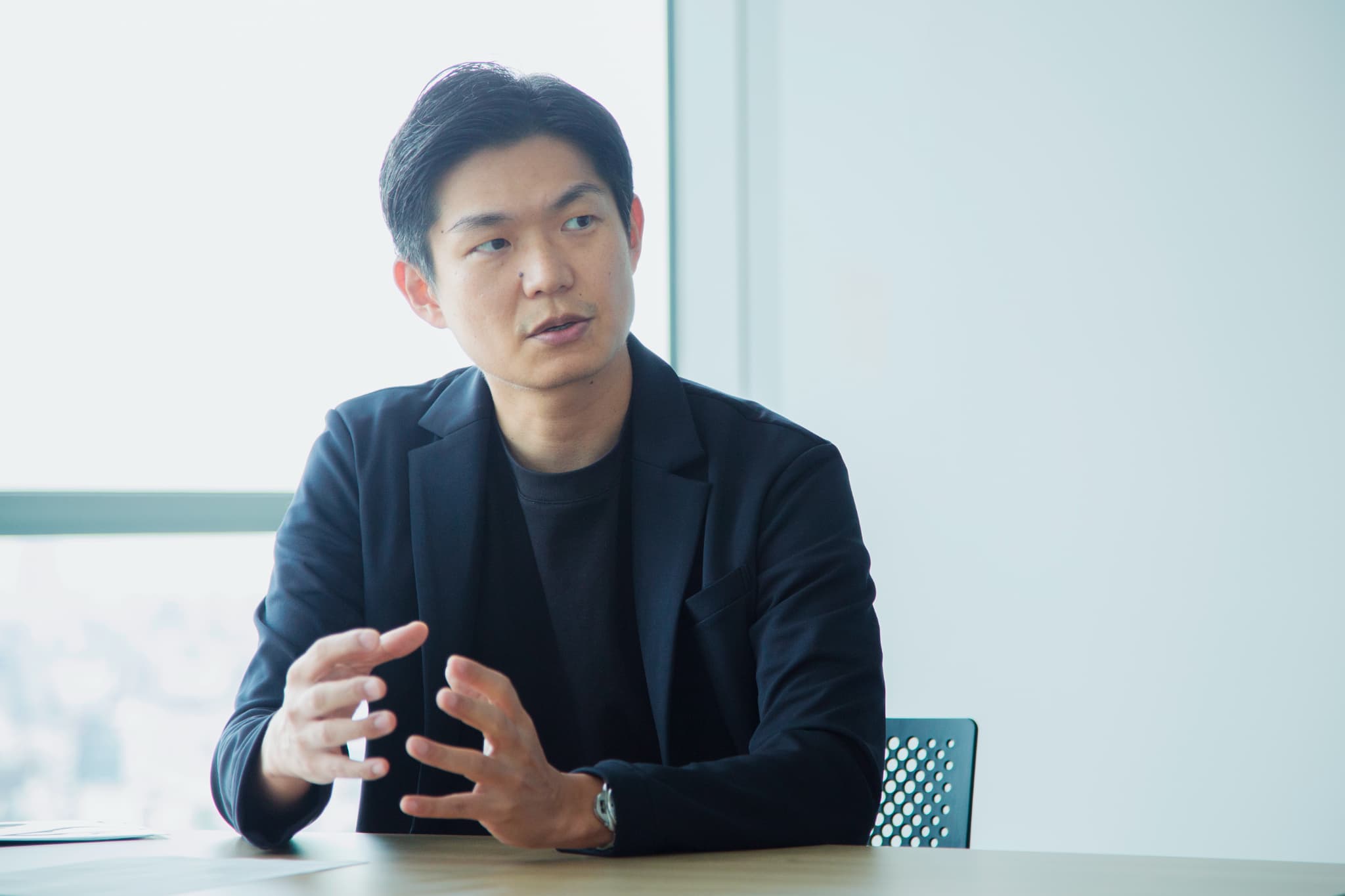
草の根的にM&Aを進め、マレーシアNo.1の事業規模を誇るクリニックに
クリニック事業参入から4年間で、クリニック数は18から154施設(2024年11月時点)に増え、マレーシアNo.1の事業規模にまで成長しています。どのようにクリニック数を増やしてきたのですか?
川副 まず、マレーシアで民間医療クリニックを経営するCareClinics Healthcare Services(以下、CCHS)への出資からスタートしました。この出資自体かなり難航しましたね。参画直前にマレーシアでもコロナパンデミックがはじまり、当時東京勤務だった私や他のメンバーも現地に出張できなくなり、現地パートナーとの合弁交渉も全てオンラインとなってしまったのです。また、当初の18施設をCCHSに統合する手続きにおいても、介在する企業数が多く、大変な数の契約になりました。コロナによってCCHSの事業も大きく影響を受けていた中、上司や法務部をはじめとするコーポレート部隊の支援もあって、やっと実現した案件でした。その後、CCHSによる現地クリニックの地道なM&Aを通じて、徐々にチェーン展開を拡大していったのです。


M&Aのプロセスは苦労も多いのではないでしょうか?
川副 マレーシアのクリニックも日本と同様に、ほとんどが個人経営。長年大切に育ててきた事業なので開業医の思い入れは強く、M&Aも一筋縄ではいきません。金額などの経済的な条件はもちろん、「自分の育てたクリニックを買収後もしっかりと面倒を見てくれるか」を非常に気にしているので、そうした思いを尊重しながら、時には何度も打ち合わせを重ねるなど丁寧にすり合わせ、交渉を進めます。
CCHSの場合、パートナーである現地の医師に主に交渉に当たってもらうことで、医師同士の深い対話が先方の安心材料になっていると思います。買収先の選定はパートナーである医師のネットワークを活用するケースが多いのですが、事業が拡大するにつれ、クリニック側からのアプローチも増えています。立地や収益性などの観点でシビアに判断し、M&Aを実施していますね。
買収の直前や当日に開業医と一緒にクリニックのスタッフにあいさつしにいくと、これまで彼らがクリニックで過ごした日々やさまざまな苦労を思い出してか、開業医やスタッフが涙ぐむこともあります。その姿を見て、事業を引き継ぐ立場として、彼らと一緒にクリニックをさらに成長させなければと、思いを新たにします。

買収・合併した後の新たな体制づくりで心がけていることはなんでしょうか?
川副 買収するまでも大変ですが、一番苦労するのは、買収後。私たちとしては、買収・合併後もできる限り既存の医師やスタッフに勤務してもらいたいのですが、買収された側はやはり不安を感じるもの。実は最初の案件では、買収直後に医療スタッフのほとんどが辞めてしまうという出来事があり、その時は本当に焦りました。最初の案件なのに、買収して早々事業をやめることになったらどうしようと、最悪の事態も想定しましたが、当時クリニックの統合担当をしていた同僚が、24時間営業のクリニックに連日泊まり込みで運営のサポートやスタッフとのコミュニケーションを進めてくれました。
私も、1対1のコミュニケーションを通じて、彼らの不安がなくなるように努めました。そのかいもあり、中心メンバーは残ってくれ、その後そのクリニックは我々の事業に大きく貢献してくれています。そのハードな場面を一緒に乗り越えた同僚、クリニックスタッフとは特別な連帯感が芽生えた気がしていますね。

そうした出来事も踏まえて、現在は買収後の統合業務を担う専門チームを設けるなど、日々体制をブラッシュアップしています。買収後、最初の1カ月は専門チームがクリニックに伴走し、CCHSグループに入ることのメリットを医師やスタッフに説明したり、新しく導入するシステムの使い方を支援したり、クリニック側に負荷が掛からないような仕組みづくりに腐心しています。
オペレーションの標準化は日々進めていますが、医師の治療・薬の処方方針、意思決定の方法、スタッフのバックグラウンドなどはクリニックごとに異なります。統合業務について、そのチェックリストは統一していますが、進め方は極力個々の専門チームのメンバーの裁量に任せるようにしています。また、買収先から我々が学ぶことも多いです。例えば、患者からフィードバックを集めるポスターは、CCHSのものより買収したクリニックのものの方が良かったので、それを他の施設にも展開するなど、患者や事業にとってのベストを常に考えるようにしています。
住商のチェーンストアオペレーションやDXを活用して「より良い医療を、より安く」
クリニック運営には、住商が小売事業でこれまで培ってきたノウハウを生かしているということですが、具体的にはどのような取り組みですか?
川副 クリニック事業は、チェーンストア事業に近いので、標準化の仕組みを構築することが、成功の一つのポイントです。住商はスーパーマーケットの「サミット」やドラッグストアの「トモズ」など小売事業を手がけていますが、商圏分析・従業員教育・薬の調達などでこれまで培ってきたオペレーションのノウハウが生きています。従業員教育におけるマニュアルなども、国は違えど生かせる部分が大いにあるなと感じています。
また、標準化という観点では、DXの推進も欠かせません。全クリニックで電子カルテを導入したり、オペレーション全体をデジタル化したりして、従業員の負担削減を図っています。

そうした取り組みの結果、M&A後のクリニックにどのような変化が見られていますか?
川副 システム導入による作業効率化や待ち時間の解消に加え、改装を施すケースではクリニックがきれいになったと患者さんに喜ばれることが多いです。また、各クリニックの医師同士で連携を取って治療方針を確立させることで、医療の質の改善も見られています。
最後に、マレーシアのクリニック事業を含め、東南アジアにおけるヘルスケア事業の展望を聞かせてください。
磯部 マレーシアのクリニック事業は、まずは300施設、その後事業の進捗を見つつ将来的には500施設とさらなる拡大を目指しており、現在のところ順調に推移しています。また、施設数だけでなく、フィジオセラピー(理学療法)、眼科、歯科、健診センターなど他業態にもサービスを拡充していきたいですね。
川副 そうですね。東南アジアでは、症状が出てからクリニックに来院されるケースがほとんどですが、一歩進んで未病・予防の観点で貢献できるプライマリケアサービスを提供していきたいです。
磯部 私たちが目指すのは、「より良い医療を、より安く」という、ある意味相反する二つの未来の両立。難しいチャレンジですが、世界のヘルスケアに貢献する意識を持って、ユニット一丸となって粘り強く事業展開を進めていきたいですね。